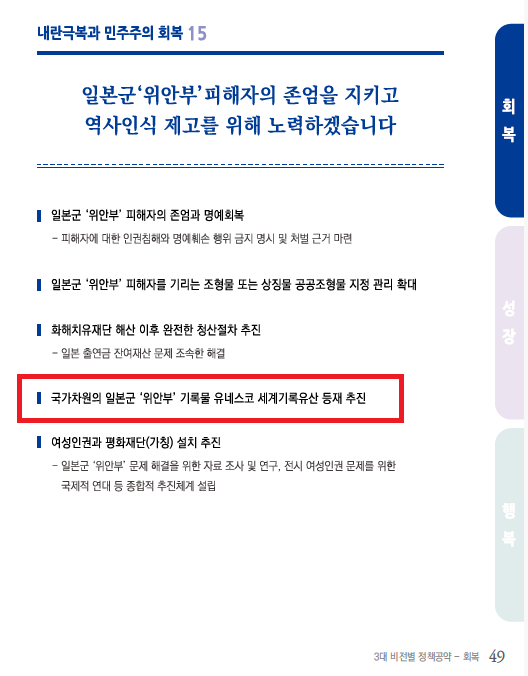著者:白松繫(しらまつ しげる)
書名:『真珠湾 ルーズベルトは知っていたー「騙し討ち」説を覆す15の証明』(ミネルヴァ書房 2025年)
[英語書名 Pearl Harbor Attack: Roosevelt knew it – 15 proofs that overturn the “Sneak Attack” theory]
評者:杉原誠四郎(国際歴史論戦研究所 会長)
(1)1941年(昭和16年)の日米開戦の戦端となった日本海軍の真珠湾奇襲について、アメリカ大統領ルーズベルトは事前に知っていたかどうかをはっきりさせることは、アメリカの戦後史の重大な課題である。
奇襲の翌日の大統領の議会での演説の時点では、議員の誰もが想像しなかったことだが、真珠湾攻撃の規模の大きさと被害の深刻さから、やがて、ルーズベルトは知っていたにかかわらず、それを真珠湾の基地に伝えず、それで被害が大きくなったのではないか、という疑念は自ずと芽生えた。
ともあれ、あれだけ大規模な攻撃を事前に察知できず、あれだけの被害を受けることになったのか、それはアメリカ国民の重大な関心事であり、その解明は歴史的にも重大なる課題だった。そのことを調べるために、戦時下で8回、戦争終直後上下両議会合同の調査委員会を含めて計9回の公的な調査が行われた。
このうち、ルーズベルトは日本海軍の奇襲を事前に知っていたのではないかという疑念を最も強く抱いてかつ大規模に行われたのは、言うまでもなく1945年(昭和20年)11月15日から翌年1946年5月31日までに行われた上下両院合同調査委員会の調査である。が、これだけ大規模に調査されながらも、ルーズベルトは知っていたという証言は得られず、なおかつそれを示す証拠となる資料も得られなかった。
こうしてしばらくは真珠湾問題に関する関係文書は非公開のままに進み、ルーズベルトは知っていたかという問題は凍結状態になるわけである。
(2)が、それでも、真珠湾攻撃があって約40年後、上記の公開調査の資料を使って、アメリカで広く読まれることになる本が2つ出た。
1つは1981年に出たGordon W. Prange, At Dawn We Slept: The Untold Story of Pearl Harbor ( McGraw Hill, 1981.) である。他は1982年に出たJohn Toland, Infamy: Pearl Harbor and Its Aftermath ( Doubleday, 1982) である。
この2つの本は、同一の資料を使いながら、両者の結論は全く反対だった。
前者プランゲの結論は、この本の最後に書いてあるように、「1981年5月1日までに世に出たすべての出版物を含む、30年以上にも及ぶ徹底的な資料調査をもってしても、我々はルーズベルトと真珠湾攻撃に関する修正主義者の立場を立証するような一編の資料も発見しなかったし、正式な証言の中にもそうしたものは一言もないのである」ということになっていた。
これに対して後者のトーランドの本ではルーズベルトは知っていたと真反対の結論を出したのである。その1つ強力な根拠としたのは、上記9回の公式の調査では出てこなかったが、サンフランシスコの第12海軍区のZなる無線士が機動部隊から出たと思われる電波をとらえ、機動部隊の位置を把握し、それをワシントンに報告していたという証言を載せていた。それが事実ならば、もはやルーズベルトは知っていたと言うよりほかはない。しかしこの時点では、日本の軍事史学では、真珠湾を攻撃した機動部隊は無線封止を厳守したということになっており、それがアメリカにも影響して、Zなる無線士の証言は十分には信頼されず、トーランドの説はアメリカで多く読まれながらも、アメリカではいまだ賛成しかねると見る見方が大勢となった。
もともとアメリカでは日米戦争を正義の戦争として戦ったわけで、ルーズベルトは知っていたとして、真珠湾の犠牲者はルーズベルトによって犠牲者となったとは信じたくないという心理的構造の中にあったので、トーランドの本を興味深くは読んだけれども、ルーズベルトは知っていたという完全なる証拠はないということで、ルーズベルトは知っていたという予知説には与しなかったといえよう。
(3)が、それから約10年経て真珠湾50周年に当たる1991年(平成3年)、アメリカ国防総省安全保障局(NSA)は、ルーズベルトの予知説に終止符を打つべく、真珠湾50周年を前にして解禁をした極秘文書を調査して、アメリカ海軍は日本海軍の真珠湾奇襲を予期できなかったと結論づけたとして発表した。が、この年に日本で出た今野勉『真珠湾奇襲-ルーズベルトは知っていたか』(読売新聞社 1991年)は、それに明確に反する結論を出していた。直接証拠とはいえないが、傍証となるルーズベルトは予知していたという世界に広がっている、そして史料的価値のあることを否定することのできない7つの証言を逐一検証し、この7つの証言は、それぞれ別の情況を証言しているのだが、それらを検証すると、時と場所を超えて全て整合し符合している、ということを明らかにしたのだ。直接証拠に基づくものではないとしても、ルーズベルト予知説が正しいことを明確に印象づけることは確かである。
その中の1つ、上記トーランドの本で、機動部隊から出てくる電波を見つけて機動部隊の位置を把握してワシントンに報告していたという話であるが、これにつきこの今野の本では、機動部隊が淡路島くらいの広がりをもって北太平洋を航行すれば、船橋から機動部隊に向けて発信する電波が機動部隊が鏡のようになって反射し、そこから新たに電波が発信されたかのような効果が出てくることがあるという説を紹介していた。この説が成り立つのであれば、機動部隊は厳しく電波発信を封じていたということと、アメリカ海軍で機動部隊から出てくる電波を分析して機動部隊の位置を把握してワシントンに報告していたという証言が両立する。
(4)それから約10年、2000年(平成12年)、Robert B. Stinnett, Day of Deceit: The Truth about FDR and Pearl Harbor, (New York: Free Press, 2000 )という研究書が出た。日米開戦前後の海軍の関係文書が歴史史料として公開され、アクセスできるようになり、ルーズベルト予知説の研究は新たな展開を始めるようになったのだ。
スティネットは、海軍に保管されていた真珠湾問題に関する日本海軍の発する電波の受信記録等にアクセスし、日本海軍の動きは相当程度明らかになっており、その情報を持っていたワシントンの中枢は、それらの情報を真珠湾の基地に伝えていなかったということが、史料に基いて主張できるようになったのだ。因みに、上記トーランドの指摘した実名を示さないままのZなる無線士については、ロバート・オグという名前を出して、その上で彼が指摘していた機動部隊の発信した電波をとらえたことを示す原史料を掲げているオグの写真を掲載しているのだ。ゆえに、トーランドの主張は正しかったということが決定的に証明されたのだ。
(5)それから25年を経た2025年(令和7年)、日本人の白松繫が、上記スティネットもアクセスして分析していなかった史料にもアクセスし、日本海軍が解読されえないと確信して使用していたD暗号も、必要な程度に一定程度解読していたことを明らかにしたのだ。そして世界で出版されている真珠湾問題の研究書を渉猟し、この書評の対象である『真珠湾攻撃 ルーズベルトは知っていた-「騙し討ち」説を覆す15の証明』(ミネルヴァ書房 2025年) を出版した。
白松には本書の出版前に『そのとき、空母はいなかった-検証パールハーバー』(文芸春秋 2013年)があるが、その後、さらに世界の関連研究書を渉猟、検討し、さらに次のような重要な史実を加えた。
真珠湾攻撃の12月7日(アメリカ暦)の3日前の12月4日に『シカゴ・デイリー・トリビューン』で1千万人動員の戦争計画が載り、ルーズベルトは大変な窮地に陥ったことになるのだが、これはチャーチルが仕組み、ルーズベルトが承認した意図的漏洩だったのだ。1940年(昭和15年)、戦争はしないという反戦の誓いをして大統領3選に成功したルーズベルトとしては、このような戦争計画を作成すること自体が国民への裏切りであるともいえ、これが暴露されることは、ルーズベルトとしては途方もない窮地に陥ることになる。上記のトーランドの本では、この漏洩事件についてルーズベルトがいかに狼狽しているかを記していることで終わっている。が、この白松の本書では、これはチャーチルとルーズベルトが仕組んだ意図的漏洩であったことを明らかにしている。
なぜそんなことをしたのか。目的は、日本海軍の真珠湾攻撃を知っていて、それを前提に、その開戦のあった後に、参戦義務の生じないドイツが対米参戦に必ず踏み切るように仕向けるためだった。これほど大規模な戦争計画をヒトラーが知るところとなれば、ヒトラーはアメリカとの戦争は不可避であると判断し、それならばそのための準備の未だ整っていないこの時点で宣戦布告をする以外にはないとして、ヒトラーはアメリカに向けて宣戦布告に踏み切るであろう、と踏んだのである。ヒトラーは悩みに悩んだあげく、12月11日に対米宣戦布告をする。
本書はその漏洩事件のからくりを日本で初めて紹介したことになる。かくしてルーズベルトの真珠湾予知説は完全に証明されたのである。日本人の手によって、ルーズベルトの予知説を完全に証明できたことを明らかにすることは、日米両国において、戦後の歴史研究において画期的ななことである。
(6)が、そもそも日米はルーズベルトの予知説に、歴史の問題として、どうして拘るのか。考えてみると、その拘りの意義は日米でその大きさに大きな差がある。アメリカでは、極端に言えば、ルーズベルトは日本海軍の真珠湾奇襲を知っていたのに、それを真珠湾の基地に知らせず、それゆえに真珠湾にいた多くのアメリカ兵が理由なく犠牲となったということの問題である。が、日本は「騙し討ち」をしたとして卑怯な国だと糾弾されて苛酷な戦争を強いられたことに鑑みれば、ルーズベルト予知説を証明することはもっと大きな意義をもっている。
奇しくも、日本側では、「宣戦布告」として見なしうるのかという問題があるものの、真珠湾攻撃開始の30分前に「最後通告」を国務長官に手交するはずであった。が、ワシントンの日本大使館の事務失態で、真珠湾攻撃開始後の手交となった。形の上ではまさに無通告の「騙し討ち」になってしまったのだ。アメリカ国民は本来の予定の経緯における場合より遥かに激しく怒ることになった。
アメリカ国民のその激しい怒りを根拠に、ルーズベルトは1943年(昭和18年)1月24日、カサブランカで、日本やドイツの無条件降伏を宣言した。日本に対しては、さらに1945年(昭和20年)2月8日、ルーズベルトはヤルタでスターリンとの間で、ドイツ降伏後の2~3カ月後に日ソ中立条約を破棄して対日参戦をするという密約を結んだ。翌日それを知ったチャーチルは、ソ連が対日参戦することになったことを日本に通知すれば、日本は降伏することは確かであろうから、戦争の被害をこの時点で終わりにすることができるとアドバイスをしたが、ルーズベルトは耳を貸さなかった。結局、それ以降の日米の戦争犠牲者は、アメリカの勝利ということをはっきりさせた上で戦争を終結させることができるのにそれをしなくて、そのために犠牲になった人たちだ。日本側で言えば、原爆や東京空襲で亡くなった人が戦争の勝敗とは関係なく犠牲となったことが分かる。それだけでなく、ルーズベルトの誘いによるソ連参戦の結果は、ルーズベルトとして日本を分断し壊滅させることになり、ルーズベルトはそうしようとしていたのだということになる。
ルーズベルトがハル・ノートを突きつけ日本を戦争に向けて挑発していたことは、上記の上下両院合同調査委員会の調査で分かった。また、日本の外交電報をことごとく解読して読んでいたことが判明したことから、日本は本来、真珠湾攻撃30分前に「最後通告」を手交しようとしており、全くの無通告で真珠湾を攻撃しようとしていたわけではないこともこの調査委員会の調査で分かった。
が、ルーズベルトは日本海軍の真珠湾を攻撃を事前に知っていたということが不明だということに依りかかる形で、日本国民に不当な困苦を与え、日本を分断国家の運命を押しつけようとしていたことが無視されてきた。そしてアメリカでは日本海軍の真珠湾攻撃を知りながら現地の真珠湾基地にそのことを知らせず、真珠湾のアメリカ兵が不当に犠牲となったということのみならず、戦争の勝敗を超えて戦争を拡大し、死ななくてよいはずの多くのアメリカ兵が犠牲にしたことを不問にしてきた。こうしたことを、アメリカ国民に明確に認知させなければならない。
ルーズベルトは、日米戦争は自らが日本を挑発して始まった戦争であることを自覚したまま、そして無通告の真珠湾攻撃は必ずしも計画的になしたものではないことを知ったまま、かくも必要以上にアメリカ兵の犠牲を増やしてまで、かくも日本に苛酷な運命を押しつけようとしていたのだ。統計によれば、日米戦争のアメリカ兵の犠牲者の半数以上は、事実上日米戦争の勝敗が決した1944年(昭和19年)7月のサイパン陥落以降に出ている。すなわち、日米戦争において、アメリカ兵の犠牲の半数以上は、日米戦争の勝敗が決してから供されているのだ。そのことの認知は、アメリカ国民と日本国民とで分かちあってよいはずだ。
そのためには、いかにせよ、ルーズベルトの予知説を完膚なきまでに証明しなければならない。ルーズベルトの日本海軍の真珠湾攻撃を事前に知っていたという予知説を、史料の完全調査とともにすべての研究書を総括して完膚なきまでに証明した本書は、歴史に関わる研究書として、今後長く光り輝くであろう。
最後に、著者は本書の英語版を出版する計画を持っていることを伝えておきたい。